オーラルフレイルを防ぐ口のトレーニング
オーラルフレイルを防ぐ口のトレーニング7選を紹介。
- ①舌の体操「ベー体操」
- ②唇を使った発声練習
- ③食事中の噛む回数を意識
- ④唾液腺マッサージ
- ⑤ガムを使った咀嚼トレーニング
- ⑥「あいうえお体操」で表情筋を鍛える
- ⑦歯科での口腔リハビリを活用
どれも自宅で簡単にできるものばかりなので、ぜひ試してみてくださいね!
①舌の体操「ベー体操」
「ベー体操」は、舌の筋力アップに効果的なトレーニングです。
やり方はとってもシンプルで、思いっきり舌を前に突き出して「べー」と声を出すだけ。
これを1セット10回ほど繰り返すことで、舌の可動域が広がり、飲み込みや滑舌の改善に繋がります。
ポイントは、鏡を見ながら舌をまっすぐ出すこと。左右に曲がったり、力が入らない場合は筋力が落ちている証拠かも。
毎日の歯磨き後など、ルーティンに組み込んで習慣化すると続けやすいですよ〜!

②唇を使った発声練習
唇まわりの筋力を鍛えるには、発声トレーニングがとっても効果的です。
特に「パ行」の音は唇の閉じる力を強化してくれます。
「パピプペポ」をリズムよく繰り返したり、早口言葉を使うのもいいトレーニングになります。
たとえば「パパパ・パパパ・パパパパ」など、ゲーム感覚でやってみてください。
唇をしっかり閉じることを意識すると、発音も明瞭になってきますよ!
③食事中の噛む回数を意識
意外と侮れないのが「噛む回数を増やすこと」です。
昔は「一口30回噛みましょう」とよく言われましたが、これって実はオーラルフレイル対策にもなるんです。
噛むことで、唾液が出やすくなり、消化吸収もスムーズに。
さらに、顔まわりの筋肉も動かすので、表情筋のトレーニングにもなるんですよ。
普段、柔らかいものばかり食べていると噛む回数が激減するので、意識して噛む練習をしていきましょう!
④唾液腺マッサージ
唾液が少ないと食事や会話がしにくくなるし、口臭や虫歯のリスクも高まります。
そんな時におすすめなのが「唾液腺マッサージ」です。
耳の前、あごの下、舌の付け根あたりを指で優しくくるくるとマッサージしてみてください。
1日2〜3回やるだけでも、唾液の分泌が促され、口の中が潤いやすくなります。
テレビを見ながらや、湯船に浸かりながらリラックスして行うと効果倍増ですよ〜!
⑤ガムを使った咀嚼トレーニング
お菓子感覚でできる「ガムトレ」は、楽しく噛む力を養える方法です。
片側だけで噛まず、左右バランスよく噛むことで、口全体の筋肉が刺激されます。
最初は数分でOKですが、慣れてきたら10分程度噛むのが理想です。
無糖ガムを選ぶと、虫歯のリスクも下がって一石二鳥ですね!
ガムが苦手な方は、乾燥昆布や小魚など、噛みごたえのある食材でも代用できますよ。
⑥「あいうえお体操」で表情筋を鍛える

「あいうえお体操」は、口まわりの表情筋を総合的に鍛えられる最強トレーニングです。
やり方は簡単で、「あ・い・う・え・お」を1文字ずつ大きくゆっくり発音するだけ。
特に大きく口を開ける「い」と「う」は、頬やあごにしっかり効きます。
鏡を見ながら毎日2〜3セット繰り返せば、見た目もイキイキしてきますよ!
表情筋が衰えると、気分まで沈みがちになるので、ぜひ明るい表情を取り戻しましょう!
⑦歯科での口腔リハビリを活用
「自分ではなかなか続かない…」という方におすすめなのが、歯科医院での専門的な口腔リハビリです。
最近では、摂食嚥下リハビリに特化したプログラムを導入している歯科医院も増えています。
理学療法士や言語聴覚士と連携して、噛む・飲み込む・話す力を総合的に鍛えることが可能です。
症状に合わせたプランを提案してもらえるので、「何から始めればいいかわからない…」という方にピッタリ。
定期的なメンテナンスとして通うのも、予防の一環になりますよ〜!
食事・生活習慣から見直すオーラルフレイル対策
食事・生活習慣から見直すオーラルフレイル対策について解説します。
- ①栄養バランスの良い食事を意識
- ②間食で噛む回数を増やす工夫
- ③会話の機会を意識的に持つ
- ④禁煙・口腔内乾燥の予防策
ちょっとした日常の見直しが、実はとっても大きな予防につながるんですよ。
①栄養バランスの良い食事を意識
オーラルフレイルの進行を防ぐためには、食事内容を整えることが基本中の基本です。
特に高齢になると「柔らかくて食べやすいもの」に偏りがちですが、噛む刺激のある食材を取り入れることが大切です。
主食・主菜・副菜をバランスよく取り入れ、タンパク質(肉・魚・卵・大豆製品)をしっかり摂るように意識しましょう。
ビタミンB群や亜鉛など、口腔粘膜の健康に関わる栄養素も忘れずに。
毎日の食事が「口の健康を保つ薬」だと思って、積極的に選んでいきたいですね!
②間食で噛む回数を増やす工夫
間食というと「おやつ=甘いもの」というイメージがありますが、オーラルフレイル対策として活用するなら「噛みごたえ」がキーワードです。
たとえば、するめ、昆布、小魚、ナッツなど、しっかり噛まないと食べられない食材がおすすめ。
これらを取り入れることで、噛む筋肉が鍛えられるだけでなく、唾液も自然に出てきます。
特に1日中マスクをしていると無意識に口を動かさなくなるので、意識的に噛む時間を作ることが重要です。
お茶の時間にちょっとした「噛むおやつ」を取り入れると、楽しみながらトレーニングできますよ!
③会話の機会を意識的に持つ
口の機能は、食べるだけじゃなく「話す」ことでも鍛えられます。
特に一人暮らしの方や、日中に人と話す機会が少ない方は、意識的に会話をすることが重要です。
電話でもオンラインでもOK。声を出すこと自体が、唇・舌・表情筋のトレーニングになるんですよ。
また、誰かと笑いながら話すことで、気分も前向きになりますよね。
気がついたら「あれ?最近、全然しゃべってないな…」という日が続いていたら要注意です!
④禁煙・口腔内乾燥の予防策
喫煙は口腔内の乾燥を招き、唾液の分泌を妨げる大きな原因になります。
唾液が少ないと、虫歯・歯周病・口臭のリスクが一気に高まり、オーラルフレイルにも直結します。
禁煙をするだけで、唾液の質と量は改善されていくと言われているんですよ。
また、部屋の湿度を保つ、こまめな水分補給、口腔内の保湿ジェルなども効果的です。
「のどが渇いた」と感じる前にケアをするのが、オーラルフレイル予防のコツですよ!
歯科医院でできるサポートと専門的ケア
歯科医院でできるサポートと専門的ケアについて紹介します。
- ①定期検診とプロのクリーニング
- ②摂食嚥下の専門的トレーニング
- ③フレイル外来・訪問診療の活用
- ④歯科医と連携した多職種ケア
「口の機能低下かな?」と感じたら、まずは歯科医院に相談するのが安心です。
①定期検診とプロのクリーニング
オーラルフレイル予防の第一歩は、やっぱり「定期的な歯科受診」です。
虫歯や歯周病の早期発見・治療はもちろん、口腔内の状態をチェックしてもらうことが最大の予防策になります。
プロによるクリーニングでは、普段の歯みがきでは落としきれない汚れを除去してもらえます。
これにより、炎症や感染のリスクを下げることができ、噛む力をしっかり保つための土台が整います。
自覚症状がなくても、3〜6ヶ月ごとの定期受診を習慣にしておくと安心ですよ〜!
②摂食嚥下の専門的トレーニング
飲み込みや噛む力が弱ってきたと感じる方には、「摂食嚥下リハビリ」が効果的です。
これは、言語聴覚士や歯科医師が連携して行う専門的なトレーニングで、食べる力や飲み込む力を鍛え直します。
嚥下障害が進行すると誤嚥性肺炎などの重大な健康リスクにつながるので、早めの対応がカギ。
リハビリでは、頬や舌の運動、姿勢の調整、呼吸法のトレーニングなどを組み合わせて行います。
自宅ではできない部分だからこそ、専門の指導を受けることで安心して食事ができるようになりますよ!
③フレイル外来・訪問診療の活用
最近では「フレイル外来」や「オーラルフレイル専門外来」を設置している歯科医院も増えてきました。
これらの外来では、全身のフレイル状態と口腔機能の関係を総合的に診てくれるんです。
特に高齢者や通院が難しい方には「訪問歯科診療」もおすすめ。
自宅や施設に歯科医が来てくれて、定期チェックや口腔ケアを受けられるので安心です。
「病院に行くのが大変」と諦める前に、こうしたサービスをうまく活用してみてくださいね。
④歯科医と連携した多職種ケア
オーラルフレイルは「口の問題」だけにとどまりません。
食事、運動、精神面…いろんな分野とつながっているからこそ、多職種の連携がとても重要です。
歯科医、栄養士、理学療法士、ケアマネージャー、訪問看護師など、さまざまな職種がチームとなってサポートする体制が整ってきています。
一人で頑張らなくても、専門家たちが一緒に寄り添ってくれるんです。
家族や介護スタッフと情報を共有しながら、総合的なケアを受けることで、長く健康な生活が送れるようになりますよ!
家族や周囲ができるサポートと声かけの工夫
家族や周囲ができるサポートと声かけの工夫について解説します。
- ①変化に早く気づくための観察ポイント
- ②本人の自尊心を傷つけない声かけ
- ③楽しく続けられる工夫を一緒に考える
- ④家族で取り組む「食」と「会話」の時間
オーラルフレイルは「ひとりの問題」ではなく、家族や周りの理解とサポートがあってこそ防げるものなんです。
①変化に早く気づくための観察ポイント
毎日一緒にいると気づきにくいですが、「あれ?最近ちょっと違うかも?」と感じる小さな変化がオーラルフレイルのサインかもしれません。
たとえば、食べるスピードが遅くなった、口を動かすのがつらそう、むせる回数が増えた、など。
滑舌が悪くなったり、会話を避けるようになったときも要注意です。
本人が気づいていない場合も多いので、家族がちょっとした変化に敏感でいることがすごく大切なんですよ。
気づいたらそっとサポートを始めてみてくださいね。
②本人の自尊心を傷つけない声かけ
「最近むせるね」「ちゃんと噛めてる?」など、心配するあまりついストレートな言い方になってしまいがちですよね。
でも、加齢による変化を指摘されるのは、本人にとってちょっとしたショックになることもあるんです。
そんな時は、「一緒に体操してみよう!」「最近このガム美味しいって話題らしいよ!」など、ポジティブな言い回しに変えてみてください。
さりげなく誘導するような声かけのほうが、やる気を引き出せることも多いんですよ。
本人の気持ちに寄り添う姿勢を忘れずに、優しい関わりを意識しましょう。
③楽しく続けられる工夫を一緒に考える
どんなに良いトレーニングも、面倒くさくなってしまえば続きません。
だからこそ「楽しく続けられる工夫」がとっても大事なんです。
たとえば、テレビを見ながら一緒に口の体操をする、カレンダーにチェックを入れてゲーム感覚で記録するなど、ちょっとした工夫で習慣化しやすくなります。
お孫さんと一緒に「あいうえお体操」をするのも、笑顔になれて最高の時間になりますよね!
「やらなきゃ」ではなく「一緒にやろう」というスタンスで、自然に取り入れてみてくださいね。
④家族で取り組む「食」と「会話」の時間
オーラルフレイルを防ぐ最も効果的な方法のひとつが、「誰かと一緒に食べること」です。
家族そろって食卓を囲むことで、自然と会話も増え、口を動かす機会がグッと増えます。
また、食事を楽しみに感じることで、噛む力・飲み込む力も無意識に鍛えられていくんです。
最近は「孤食」と言われるようなひとりの食事が増えていますが、それがオーラルフレイルの一因になることも。
日々の中で「一緒に食べよう」「話しながらご飯しよう」という時間を意識してみてください。
その積み重ねが、心の健康にもつながっていきますよ。
まとめ
オーラルフレイルは、放っておくと全身の健康に影響を及ぼす「口の機能低下」です。
むせ、噛みにくさ、会話のしづらさなど、ちょっとした変化がそのサインかもしれません。
早めに気づき、自宅でのチェックやトレーニングを習慣化することで、進行を防ぐことが可能です。
また、歯科での専門的なケアや、家族のあたたかいサポートが、予防と改善の大きな力になります。
「まだ大丈夫」ではなく「今できることから」始めて、健康な口元と生活を守っていきましょう。
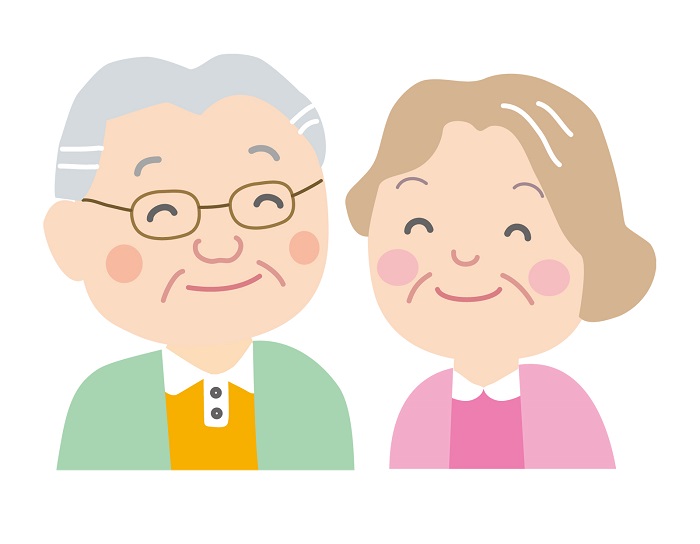
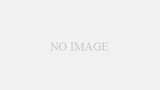
コメント