
「お米、高くなったなぁ」と思ったこと、ありませんか?
かつては5キロ1500円前後で買えていたお米が、今では4000円、5000円台も珍しくありません。
家計を預かる身としては、こうした値上げは本当に痛いところですよね。
でも、その一方で「農家のことを考えろ」「高いと文句を言うのは自分勝手」という声も聞こえてきます。
果たして、「お米が高い」と感じるのはわがままなのでしょうか?
ちょっと冷静に、そして論理的に考えてみましょう。
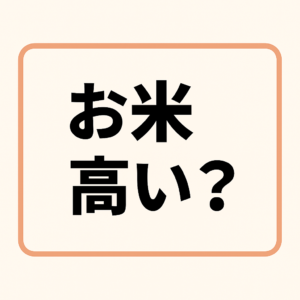
米が高いのは“感情論”ではない
まず前提として、「米が高い」と感じるのは、感情論ではなく家計へのリアルな影響です。
今の日本では、物価だけが上がり、賃金はなかなか上がっていません。
給料が増えない中で、食費や日用品が次々と値上がりしていけば、どんな家庭でも負担は大きくなります。
お米の値段だけが問題ではなく、「日々の暮らしのコスト全体が重たくなっている」からこそ、米の価格に敏感になっているんです。
農家もまた「好きで高くしている」わけじゃない
とはいえ、「じゃあ農家が儲けすぎてるのか?」というと、それはまったく違います。
実際、農家の方々も厳しい状況に置かれています。
燃料代や肥料、機械のメンテナンスなど、生産にかかるコストは年々上昇。
しかも、消費者が支払う価格のすべてが農家の収入になるわけではなく、流通の過程で中間業者による“中抜き”も発生しています。
農家自身も、「もっと米を安く売りたい。でもそれでは生活できない」という葛藤の中にいるのが現実なのです。
「趣味を削れ」は本質的な解決にならない
よくSNSなどでは、「米が高いって文句言うなら、趣味に使うお金を減らせば?」という意見も見かけます。
でも、これってすべての人に当てはまる話ではありませんよね?
そもそも、趣味を楽しむ余裕すらない人もたくさんいます。
生活そのものがギリギリで、娯楽費なんて真っ先に削っている家庭もある中で、「削ればいいじゃん」はちょっと乱暴すぎる話です。
問題の本質は「収入と物価のバランスが崩れていること」。
そこを無視して消費者の“我慢”だけを求めるのは、健全な議論とは言えません。
まる収入が増えていれば、不満も少なかったかもしれない
もし、日本全体の賃金水準がもっと早く上がっていれば、現在の米価でもそれほど強い不満は出なかったかもしれません。
実際、経済の専門家の中には「本来、日本人の平均年収は今より200万円ほど高くなっていたはずだ」という試算をする人もいます。

収入がきちんと増えていれば、多少の物価上昇にも対応できますし、農業支援にも前向きな意見が増えたかもしれません。
今ある不満の多くは、「生活が苦しいのに、さらに負担が増える」という現実から生まれているのです。
日本の米文化、このままだと消えるかも?
実は、今のままの構造が続くと、日本のお米文化そのものが危うくなる可能性もあります。農業は重労働にもかかわらず儲からない。
そんな状況が続けば、担い手はどんどん減っていきます。
結果として、国産米の供給量が減り、最終的には外国産に頼ることにもなりかねません。
ちなみに私は以前、イギリスの方に聞いたことがあります。
そこで売られていた日本米に近い品質のものは、10キロで2000〜3000円程度。
もちろん為替や物価水準が違うので単純に比較はできませんが、「どうして日本の米がここまで高くなるのか?」という疑問は自然なものです。
対立ではなく「共通の課題」に目を向けて
結論として、米が高いと感じる人も、農家の苦労を訴える人も、対立する必要はありません。
どちらも正しい視点を持っていて、問題の根本は「構造そのもの」にあるのです。
感情的に「自分勝手だ」「農家を守れ」とぶつかるのではなく、どうやったら農家が持続可能に働けて、消費者の負担も軽減できるかを考えていくことが大事ではないでしょうか?
食の安全や文化を守るという意味でも、日本の農業の持続可能性は無視できないテーマですね。
感情ではなく、冷静な視点で、お米の未来について一緒に考えてみませんか?



コメント