暑かった日も、やっと朝晩少し涼しくなりました。
運動会の季節になりました。
昨日も保育園の運動会でしたが暑い1日でした。
真っ青な空の下、子どもたちの元気な声が響き渡る運動会。
今では当たり前のこの行事ですが、日本でいつから始まったのか、どんな種目があって、現代にどのように変化してきたのでしょうか。
運動会の始まり〜明治の海軍兵学寮から〜
日本で初めての運動会は、明治7年(1874年)3月21日に東京・築地の海軍兵学寮(後の海軍兵学校)で開催された「競闘遊戯会」だと言われています。
これはイギリス人英語教師フレデリック・ウィリアム・ストレンジの指導によるもので、当時の日本にはまだスポーツという概念がほとんどありませんでした。
「競闘遊戯」とは難しい言葉ですが、これは「アスレチック・スポーツ」の訳語でした。
この第一回の競闘遊戯会では、10代から20代の学生たちが参加し、徒競走や二人三脚、幅跳び、高跳びなどの種目が行われたと記録されています。
今でもおなじみの種目がすでにあったことに驚きますね。
当時の日本では、明治5年(1872年)に学制が公布され、近代的な学校制度が始まったばかり。
運動会という言葉は早くからあったものの、明治初期には「運動」にスポーツの意味がまだなく、当初は現在でいう「遠足」を指していたそうです。
運動会と遠足のルーツは実は同じだったのです。
全国への広がり〜明治時代の運動会〜
この競闘遊戯会をきっかけに、運動会は明治時代半ばから全国の学校に広まっていきました。
明治11年(1878年)には、札幌農学校(現在の北海道大学)で「力芸会」が開催されました。
これは軍事色の濃い種目を減らし、教育の一環としての運動を重視した大会だったと言われています。
力芸会では、徒競走や障害物競走、綱引き、そして「食菓競争」という競技も行われました。
この「食菓競争」は、なんと現在のパン食い競争のルーツとなった競技なのです。
今の運動会の原型は、この頃にはほぼ完成していたと言えるでしょう。
そして明治16年(1882年)、東京大学で初めて「運動会」という名称を使った大会が開催されました。
これ以降、運動会という言葉が定着していくことになります。
大正時代から昭和初期〜変化する運動会〜
大正時代に入ると、新教育・自由主義教育や児童中心主義の運動が盛り上がりました。
運動会も変化を遂げ、複数の学校が合同で行う連合運動会から、学校ごとの運動会へと変わっていきました。
高いポールに万国旗や日の丸を掲げたり、オルガンの伴奏が使われたりと、形式も華やかになっていきます。
種目も競争的なものに加えて、唱歌遊戯やリズムダンス運動などが取り入れられ、より多彩になりました。
運動会は単なる競技の場から、子どもたちの表現活動の場へと広がっていったのです。
しかし、昭和12年(1937年)に日中戦争が始まると、運動会の様子は一変します。
軍事一色に染まり、名称も「体育会」「体練大会」「錬成大会」などに変わり、「皇国臣民」を養成する場になっていきました。
平和な運動会の姿が、時代の波に飲み込まれていったのです。
戦後から平成へ〜レクリエーションとしての運動会〜
戦後、運動会は再び平和なレクリエーションとして復活しました。
学校だけでなく、会社や地域ぐるみの行事として定着していったのは、この第二次世界大戦後のことです。
昭和40年代から平成の初めにかけて、運動会は最も華やかな時代を迎えます。
組体操でピラミッドやタワーを作ったり、騎馬戦や棒倒しといったダイナミックな種目が人気を集めました。
お弁当の時間も家族が集まる楽しみの一つで、運動会は一日かけて行われる一大イベントだったのです。
|
|
この時代の代表的な種目としては、徒競走、綱引き、PTA競技、玉入れ、紅白対抗リレーなどが実施率の高い上位種目でした。
これらは今でも多くの運動会で見られる定番種目ですね。
令和の運動会〜安全と時短の時代〜
そして現代。
令和の運動会は、大きな転換期を迎えています。
最も大きな変化は「時間の短縮」です。
コロナ禍を経験したこと、そして9月の猛暑日が増加したことで、熱中症対策の観点から、午前中だけで競技を終了する学校が増えています。
競技数を大幅にカットして短時間で終わらせる傾向が強まっているのです。
お弁当を家族で囲む光景も、今では見られない学校が増えてきました。
安全面への配慮も大きく変わりました。
組体操のピラミッドやタワー、騎馬戦、棒倒しといった、かつては運動会の華だった種目が、けがのリスクから中止される学校が増えています。
特に組体操や「むかで競走」でのけが人が多いことが社会の注目を集め、子どもたちの安全を第一に考える方向へとシフトしてきました。
開催時期も多様化しています。かつては10月10日の体育の日(現在のスポーツの日)前後に集中していましたが、今では春開催と秋開催がほぼ半々となっています。
真夏の猛暑を避けるため、5月や6月に実施する学校も増えているのです。

新しい運動会の形
危険な種目が減る一方で、新しい種目も生まれています。
例えば「防災運動会」のように、楽しみながら防災の知識や緊急時の対応方法を学べる種目を取り入れる学校も現れました。
運動会が単なる体力づくりの場から、生きる力を育む場へと進化しているとも言えるでしょう。
また、教職員の働き方改革の観点からも、競技種目の精選や半日開催が推奨されるようになっています。
運動会の準備や練習に割く時間の確保が難しいという現実的な問題もあるのです。
変わらないもの、変わっていくもの
明治7年の競闘遊戯会から150年。
運動会は時代とともに大きく変化してきました。
軍事訓練の場として利用された暗い時代もあれば、家族の絆を深める楽しい一日として愛された時代もありました。
現代の運動会は、安全性や効率性を重視する方向へと舵を切っています。
かつての華やかさや長時間の開催は減りましたが、それは子どもたちの安全と健康を第一に考えた結果です。
それでも変わらないものがあります。
それは、運動会が子どもたちの成長の場であり、チームワークやリーダーシップを学ぶ貴重な機会であるということ。
そして、真剣に取り組む子どもたちの姿に、保護者や地域の人々が心を動かされるということです。
昨日の保育園の運動会も暑い一日でしたが、小さな子どもたちが一生懸命走る姿、仲間と力を合わせる姿は、きっと150年前から変わらない運動会の本質を見せてくれていたのでしょう。
これからの運動会がどのように変化していくのか。
時代に合わせて形を変えながらも、子どもたちの笑顔と成長を支える場として、運動会は続いていくに違いありません。





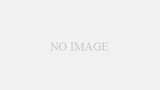
コメント